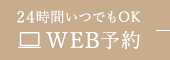健康な食生活とは?3大栄養素について~PFCバランスを考えた食事について~
2025.03.12
栄養バランスの基本~健康的な食生活を支えるポイント~
今回は、三大栄養素であるタンパク質、脂質、炭水化物の役割や、バランスの取れた食事についての考えを説明していきます。
1. 栄養素の役割
タンパク質
タンパク質は、体の構成成分のひとつであるとともに、代謝にも大きく関わっています。筋肉や内臓、酵素やホルモン、免疫物質など、
私たちの体のあらゆる部分を作り上げており、体内の代謝に欠かせません。
不足すると、体力や免疫力、思考力など体の機能の低下や基礎代謝の低下も招き得ます。
成人は、1日に体重1kgあたり約0.8~1.0gのタンパク質が必要と言われています。
また、タンパク質はビタミンB群(B1,B2,ナイアシンなど)を含むものと一緒に摂ることで、効率よく代謝することができます。
ビタミンB群は赤身魚やヒレ肉、レバー、シジミや海苔などに多く含まれます。
**タンパク質を多く含む食品:**
肉(特に鶏肉)、魚、大豆製品(豆腐や納豆)、卵、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)
脂質
脂質は1gで9kcalと身体の大きなエネルギー源となります。細胞膜の主要な構成要素であり、ホルモンの合成にも関与しています。
脂肪酸には飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があり、特に不飽和脂肪酸は健康に良い影響を与えるため、意識的に摂取することが推奨されています。
しかし、体内で消費せずに余った分は体脂肪として蓄えられ、貯蔵エネルギーともなりますが、
過剰摂取は肥満や生活習慣病のリスクを高める恐れがあります。
脂質を多く含む食品を摂る際は量に注意しましょう!
**脂質を多く含む食品:**
バター、アボカド、ナッツ、オリーブオイル、生クリーム、バラ肉、魚(特にサーモンやマグロ)
炭水化物
炭水化物は、私たちの体の主なエネルギー源であり、タンパク質や脂質と比べてエネルギーへの変換が早く、脳や神経系、筋肉の活動に必要不可欠です。
また、遺伝情報を担うDNAやRNAなどの構成成分にもなります。
炭水化物は摂りすぎると中性脂肪として蓄えられ、肥満や生活習慣病の原因となります。
反対に不足すると、エネルギーが足りず、タンパク質が分解され筋肉の減少につながり、
疲労感や脱力感が感じるほか、脳の働きもにぶくなってしまいます。適正量摂ることが重要です。
**炭水化物(糖質)を多く含む食品:**
砂糖、ごはん、パン、パスタ、果物、芋類、くりなど
2. バランスの取れた食事の組み立て方
適正エネルギー量の簡単な計算方法
適正エネルギー量=標準体重(身長×身長×22)×身体活動量
身体活動量 普段の活動量
25~30 軽い労作(デスクワークが多い職業など)
30~35 普通の労作(立ち仕事が多い職業など)
35~ 思い労作(力仕事が多い職業など)
エネルギー産生栄養素
PFCバランスという言葉を聞いたことはありますか?
P:タンパク質(Protein)
F:脂質(Fat)
C:炭水化物(carbohydrate)
これらの構成成分が総エネルギー摂取量に占めるべき割合の構成比率を示したものです。
この値は各種栄養素の摂取不足を回避すること、そして生活習慣病の発症予防とその重症化予防を目的としています。
PFCの三大栄養素をバランスよく摂取することが基本です。
具体的には、以下のような比率のエネルギーで食品を組み合わせることが推奨されています。
P- タンパク質:全体の13~20%
F- 脂質:全体の20~30%
C- 炭水化物:全体の50~65%
P- タンパク質(%)=タンパク質(g)×4(kcal)÷総エネルギー摂取量(kcal)×100
F- 脂質(%)=脂質(g)×9(kcal)÷ 総エネルギー摂取量 (kcal)×100
C- 炭水化物(%)=炭水化物(g)×4(kcal)÷ 総エネルギー摂取量(kcal)×100
食事の具体例
1日の食事の一例 朝食 ライ麦パン、ベーコンエッグ、サラダ、ヨーグルト 昼食 ご飯1杯、レバニラ炒め、キュウリとカニカマの酢の物、リンゴ 夕食 もち麦入ご飯1杯、アジの開き、豆腐とワカメの味噌汁、ほうれん草のお浸し 各食に主食、主菜、副菜に加え、乳製品や果物なども入れることで、タンパク質、脂質、炭水化物を摂取することに繋がります。 上記はただの一例であり、毎日、毎食、PFCバランスを揃えることはかなり難しいことです。お肉を食べすぎてしまった次の日は野菜を多めにして主菜を魚にしたり、 飲み会で脂っこいものを食べすぎてしまったら翌日は揚げ物やアルコールは控えるというように、 まずは1日のトータル、あるいは1週間でバランス良くなるように考えてみましょう。 最近はスマートフォンで簡単に食事記録ができるアプリケーションなどもあるので、気になる方は試してみてください! MyfitnessPal←院長も愛用しているアプリです。バーコード読み取り機能も便利です。 https://www.myfitnesspal.com/ja あすけん https://www.asken.jp/info/asken-app
食生活で気を付けるポイント
多様な食品を取り入れる!
いつも同じ食品ばかり食べるのではなく、色々な食品を日々の食事に取り入れましょう!
食卓の彩りを豊かにすることで多様な食品を取り入れやすくなり、さらに見た目でも食事を楽しめます。
好きなものばかり食べたり、特定の食品を極端に避けすぎると栄養バランスを崩しやすくなるので注意が必要です。
食事の時間を規則正しくする!
不規則な食事時間は、体内時計が崩れてしまい、食習慣、生活習慣の乱れに繋がりやすいです。
お仕事などもあり、毎日同じ時間は難しいかもしれませんが、できるだけ同じ時間に食事を取り、食事のリズムを整えることも良い生活習慣に結びつきます!
食事の摂り方を意識する!
外食はエネルギー過多になりやすいので注意が必要です!特にファストフードの料理などは油脂や砂糖、塩分も多く使われているものが多いです。
近日はレストランのメニューやコンビニエンスストアの商品にエネルギーやタンパク質などの栄養価表示もされています。
自分が摂るものの表示を意識して見ることで、自分がどれだけ摂取したか把握し、摂りすぎを防ぐことにつながります!
栄養バランスを考えた食事献立の組み立て方の参考になれば幸いです。食事を楽しむことは忘れず、意識して三大栄養素を摂取していきましょう!