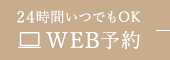水溶性ビタミンって?身体の中での役割
水溶性ビタミンの役割
脂溶性ビタミンに続き、水溶性ビタミンについての簡単な作用・我々日本人の平均摂取量・厚労省の推奨(目安)摂取量について記述します。
また、各種のビタミンの主な食品(ビタミン量)も記載するので参考にしてください。(厚労省の食品成分表)
- ビタミンB1
- ビタミンB2
- ナイアシン
- ビタミンB6
- ビタミンB12
- パントテン酸
- 葉酸
- ビオチン
- ビタミンC
ビタミンB1
別名チアミンと呼ばれているものです。
経口摂取により小腸から吸収されます。
主な作用
・糖代謝やアミノ酸代謝に関わる補酵素として働きます。
糖質(炭水化物)摂取が多いと、このビタミンB1の不足となり、代謝されずに長期的には生活習慣病のリスクとなってしまうわけです。
ビタミンB1欠乏
日本人がよる摂取する精白米を常食している場合(他にビタミンB1摂取がない場合)は、脚気(全身だるさ・体重減少・四肢の知覚障害・腱反射消失・動悸など)、
アルコールを多飲している場合は、ウェルニッケ脳症(眼球運動麻痺・歩行運動失調・意識障害など)です 。
健常な場合には、脚気を認めることはほとんどないですが、食事も摂らないでアルコールを多飲してビタミンB1欠乏となる人は見かけられます(これが慢性的に続くと精神症状(コルサコフ症候群)がでてきます)。
ビタミンB1過剰
これは水溶性ビタミンであり、摂りすぎたら排泄されるだけですので特異的な有害事象はありません。
日本人の平均摂取量
男性:平均 0.98 mg/日、女性:平均 0.84 mg/日(2018年の国民健康・栄養調査)
厚労省の推奨量(18歳-)
男性:1.2-1.4 mg/日、 女性:0.9-1.1 mg/日(2020年)
やはりお米の文化が根付いているだけあって、ビタミンB1摂取量はやや少ないです。
白米ではなく玄米だと0.16mg/100g、絹ごし豆腐 0.11mg/100g、豚ヒレ肉 2.09mg/100g、紅サケ 0.29mg/100g、ぶり 0.24mg/100gのビタミンB1を摂取することができます。
また、食べ物によってはビタミンB1を分解する酵素(チアミナーゼ)を含むものもありますので注意が必要です。貝類、山菜、淡水魚に多いと言われてますが、この酵素は加熱で失活するので食べてはいけないわけではありません。
ビタミンB2
別名リボフラビンです。
主な作用としては、脂質・糖・蛋白質代謝です。つまり、エネルギー産生の3大栄養素の異化代謝の補酵素及び電子伝達系の構成分子になります。
ビタミンB2欠乏
成長障害、口角炎、舌炎や脂漏性皮膚炎が起こります。ビタミンB2不足で代謝異常を起こすことがありますが、ビタミンB2欠乏単独では起こらないとされています。
ビタミンB2過剰
これは水溶性ビタミンであり、摂りすぎたら排泄されるだけですので特異的な有害事象はありません。(過剰にとると、排泄量が増加して尿の色がまっ黄色になるくらい?)
日本人の平均摂取量
男性:平均 1.22 mg/日、女性:平均 1.11 mg/日(2018年の国民健康・栄養調査)
厚労省の推奨量(18歳-)
男性:1.3-1.6 mg/日、 女性:1.0-1.2 mg/日(2020年)
18歳から74歳までは、厚労省の推奨量を下回っています。
食事としては、
納豆 0.22 mg/ 40 g、アーモンド 0.21 mg/ 20 g、アボガド 0.11 mg/ 50 g
牛レバー 1.2 mg/ 40 g、低脂肪牛乳 0.37 mg/ 1杯、ぶり 0.31 mg/ 80 mg
のビタミンB2を摂取できます。
ナイアシン
ナイアシンは食べ物以外から、生体内における必須アミノ酸のトリプトファンから肝臓で生合成することができます。(なんとなく不足しなさそうな感じがしますね。。。)
作用としては、糖や脂質の代謝に関与しています。(詳しくは、ATP 産生、ビタミン C・ビタミン E を介する抗酸化系、脂肪酸の生合成、ステロイドホルモンの生合成等の反応に関与、DNA の修復、合成、細胞分化に関わっています)
ナイアシン欠乏(ペラグラ)
皮膚炎、下痢、精神神経障害が起こります。
ナイアシン過剰
これは水溶性ビタミンであり、摂りすぎたら排泄されるだけですので特異的な有害事象はありません。
日本人の平均摂取量
男性:平均 32.6 mg/日、女性:平均 27.1 mg/日(2018年の国民健康・栄養調査)
厚労省の推奨量(18歳-)
男性:13-15 mg/日、 女性:10-12 mg/日(2020年)
上記のようにナイアシン平均摂取量は、厚労省の推奨量を満たしています。
主な食事としては、落花生 17mg/ 100mg、ひらたけ 10.7mg/ 100mg、玄米 6.3mg/ 100mg、えのきたけ 6.8mg/ 100mg、かつお(生) 19mg/ 100mg、キハダマグロ(生) 17.5mg/ 100mgのナイアシン摂取ができます。
ビタミンB6
主な作用は、蛋白質代謝(アミノ基転移反応)、脱炭酸反応、ラセミ化反応などに関与する酵素の補酵素として働いています。
ビタミンB6欠乏
大球性貧血、湿疹、口角炎、舌炎、脂漏性皮膚炎、麻痺性発作、聴覚過敏、免疫力低下などが起こります。
ビタミンB6過剰
これは水溶性ビタミンでありますが、過剰摂取により有害事象があります。過剰摂取時 (数カ月間で数 g/日を摂取継続した場合) には、感覚神経障害、末梢感覚神経障害、骨痛、筋肉の脆弱、精巣萎縮、精子数の減少などを起こすことが知られています。しかしながら、食品でビタミン1mgを超えるものはないため、サプリメントなどを過剰摂取しなければ問題ありません。(70㎏の人で4カ月間300mg/day摂取しても健康障害は認めない報告が出ています)
日本人の平均摂取量
男性:平均 1.24 mg/日、女性:平均 1.07 mg/日(2018年の国民健康・栄養調査)
厚労省の推奨量(18歳-)
男性:1.4 mg/日、 女性:1.1 mg/日(2020年)
厚労省の推奨量をやや下回っています。また、過剰摂取による有害事象も懸念して上限を設定しておりますが、これはかなり厳しい条件で設定されています。先ほど記載したように70kgの人でビタミンB6< 300mg/day (4.3 mg/kg体重/day)の場合は、有害事象はなかったのですが、そこからその他の因子の影響も考慮して0.86 mg/kg体重/dayまで上限をかなり下げています。)
主な食事としては、にんにく 1.53mg/100mg、ひまわりの種1.18mg/100mg、玄米 0.45mg/100mg、ゴマ 0.60mg/100mg、ささみ(生で)0.66mg/100mg、かつお 0.76mg/100mg、くろまぐろ 0.86mg/100mgのビタミンB6を摂取できます。
ビタミンB12
ビタミン B12 は、脂肪酸やアミノ酸の代謝に関与しており、メチオニンの生合成に関与するメチルビタミン B12依存性メチオニン合成酵素の補酵素として働きます。
ビタミンB12欠乏
巨赤芽球性貧血、脊髄及び脳の白質障害、末梢神経障害が起こります。内科医としては、胃の切除後で吸収障害により、葉酸欠乏と共にビタミンB12を欠乏している方や腎臓が悪く(透析患者も含む)蛋白質制限によりビタミンB12を欠乏している方を診ることがあります。
これはあくまでも個人的見解ですが、よく高齢の方で整形外科に通院している方は、足のしびれに対してビタミンB12の薬を内服していることが多く、血液検査をすると血中のビタミンB12の濃度は十分にあります。(過剰になっても問題ないですが、私が主治医の場合は、一旦内服を切ります)
ビタミンB12過剰
これは水溶性ビタミンであり、摂りすぎたら排泄されるだけですので特異的な有害事象はありません。
日本人の平均摂取量
男性:平均 6.5 μg/日、女性:平均 5.4 μg/日(2018年の国民健康・栄養調査)
厚労省の推奨量(18歳-)
男性: 2.4 μg/日、 女性:2.4 μg/日(2020年)
我が国の厚労省の推奨量は、満たしております。疾患がない方で厳格な菜食主義者でなければ、不足になることはないと思います。この推奨は、あくまでもアミノ酸・脂肪代謝に必要なビタミンB12の量を想定していますので、他の観点(疾病予防など)から量は足りない可能性もあります。
食べ物としては、しじみ 68.4 μg/ 100g、いくら 47.3 μg/ 100g、かき(生)28.1μg/ 100gののビタミンB12を摂取可能です。
パントテン酸
糖及び脂肪酸代謝に関わる補酵素の成分になります。パントテン酸は、ギリシャ語で"どこにでもある酸"という意味で、色々な食品に存在するため、欠乏症になることはほとんどありません。
パントテン酸欠乏
手足のしびれと灼熱感、頭痛、 疲労、不眠、胃不快感を伴う食欲不振などが起こります。
パントテン酸過剰
これは水溶性ビタミンであり、摂りすぎたら排泄されるだけですので特異的な有害事象はありません。
日本人の平均摂取量
男性:平均 5.96 mg/日、女性:平均 5.23 mg/日(2018年の国民健康・栄養調査)
厚労省の目安量(18歳-)
男性:5-6 mg/日、 女性:5 mg/日(2020年)
50歳以上の男性は、目安量をやや下回っています。
食事としては、ひきわり納豆4.28mg/100mg、ブロッコリー1.12mg/100mg、アボガド(生)1.65mg/100mg、黒砂糖1.38mg/100mg、オートミール1.29mg/100mgのパントテン酸を摂取できます。
前述した通り、食事摂取していれば過不足になることはないビタミンですので、通常の食事を心掛ければよいと思います。
葉酸
葉酸は、ビタミンBの一種とされており、DNA/RNA合成に関与しています。
また葉酸には、自然界にはほとんど存在しない「狭義の葉酸(プテロイルモノグルタミン酸」とポリグルタミン酸型の「食品性葉酸」に分けられます。狭義の葉酸は、サプリメントや強化食品でしか摂取は難しいのですが、葉酸の摂取量はこの「狭義の葉酸」の重量で評価しています。
葉酸欠乏
欠乏により血中ホモシステイン濃度が上昇し、動脈硬化などを来します。
造血機能が異常をきたし、ビタミンB12欠乏と同様に巨赤芽球性貧血を来したり、神経障害や腸機能障害などが起こります。
葉酸過剰
これは水溶性ビタミンであり葉酸単独では特異的な症状はありません。しかし、ビタミンB12欠乏症も併発している時に葉酸のみを補充した場合は、神経症状は悪化することが報告されているので、注意が必要です。
日本人の平均摂取量
男性:平均 295 μg/日、女性:平均 281 μg/日(2018年の国民健康・栄養調査)
厚労省の推奨量(18歳-)
男性:240 μg/日、 女性:240 μg/日(2020年)
葉酸の平均摂取量は、厚労省の推奨量を上回っています。しかしながら、胎児の神経管形成期である受胎前後から妊娠初期までの間に、母体が葉酸 (プテロイルモノグルタミン酸) を摂取すると、胎児の神経管閉鎖障害のリスクが低減されることが報告されており、神経管閉鎖障害発症の予防のために狭義の葉酸(サプリメントや食品中に強化される葉酸)として 400 µg/ 日の推奨としている。また、妊娠時(中期及び後期)は、葉酸の分解及び排泄が促進されるとする報告されており、240μg/日の付加量(通常推奨量に加えて)することが推奨されています。
食事としては、ほうれんそう(ゆで)110μg/100mg、枝豆(冷凍)310μg/100mg、ブロッコリー(ゆで)120μg/100mg、いちご 90μg/100mg、とり(肝臓、生) 1300μg/100mg、生ウニ360μg/100mgの葉酸を摂取可能です。
ビオチン
ビオチンは糖新生や脂肪酸合成に関与している補酵素であります。よく美容を意識している人は馴染みがあるビタミンでないでしょうか。
ビオチン欠乏症
乳酸アシドーシス、鱗状皮膚炎や萎縮性舌炎、食欲不振などを引き起こすことが言われております。
ビオチン過剰症
水溶性ビタミンであり、妊娠中を除いては問題ないとされています。
日本人の平均摂取量
明確なデータはありませんが、45-60μg/日程度摂取している報告があります。
厚労省の目安量(18歳-)
男性:50 μg/日、 女性:50 μg/日(2020年)
食事摂取としては、ウシレバー 96μg/100mg 、卵黄 52μg/100mgのビオチンを摂取できます。基本的には大豆や穀物に多いとされています。
ビタミンC(アスコルビン酸)
このビタミンは馴染みのある水溶性ビタミンだと思います。今後のブログでデータを出す予定ですが、美容だけでなく免疫機構にも大きく関与していると言われています。また、ビタミンEと同様で抗酸化作用があります。
ビタミンC欠乏症
皮膚や細胞のコラーゲン合成に必要であります。またコラーゲン不足により血管に影響が出るため、歯肉出血や皮下出血を起こします(病的あれば壊血病といった出血傾向を認めます)。他には貧血、筋肉減少をきたすことがあります。
ビタミンC過剰症
水溶性ビタミンであり、特異的な症状はありませんが、医薬品やサプリメントで摂取しすぎると胃腸障害をきたすこがあります。
日本人の平均摂取量
男性:平均 93 mg/日、女性:平均 97 mg/日(2018年の国民健康・栄養調査)
厚労省の推奨量(18歳-)
男性:100 mg/日、 女性:100 mg/日(2020年)
平均摂取量は厚労省の推奨量よりもやや下回ってます。また喫煙者はビタミンCの必要量が上がるため、この推奨量よりも多くなるのですが、喫煙は健康の観点からも禁煙するようにした方が良いです。(禁煙するための習慣の方法も情報発信していきますので乞うご期待)
食事は、赤ピーマン(油炒め) 180mg/100g、サツマイモ 29mg/100g、キウイフルーツ69mg/100mg、レモン(生)100mg/100g、イチゴ 69mg/100g、みかん 33mg/100gのビタミンC摂取が可能です。
よくビタミンC1000mgくらいの高濃度点滴やサプリメントを見かけますが、果たして健康の観点からはエビデンスがあるのかは疑問であります。高濃度点滴1回よりも継続的に摂取する方が好ましいと思いますが。。。(あくまでも個人的な見解です)
以上、簡単ではありますが、水溶性ビタミンについて説明しました。各々のビタミンの食事は一部抜粋をしてますので、詳しい情報は厚労省のホームページを参照してください。